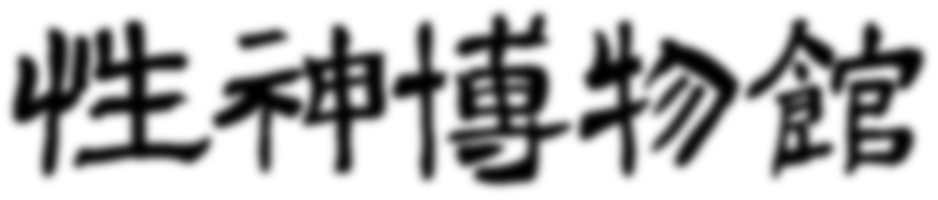コンセイ」考
「道祖神」「コンセイシン」「サイノカミ」…。性神の種類を数え上げればキリがないが、今回は「コンセイシン」について考えてみたい。
金勢、金精、金生、根清、根生、魂生。「コンセイ」様の表記は何パターンもあり、どれが元祖かはちょっと分からない。有名な「山崎のこんせい様」がある岩手県では「金勢」が多いようだが、道鏡の男根を祀ったという栃木県にある神社は「金精」が使われ、金精峠の由来にもなっている。江戸の町で遊女らに信仰されていたのも「金精」の印象が強い。いずれにしても、「コンセイ」の音は漢字であろうから、どれか大本だったものが伝えられていくうちに、様々な表記が生まれていったのであろう。
「勢」について
「勢」という字には「男子の性器」の意味がある。「大漢和辞典(大修館書店)」で調べてみると、「晋書 刑法志(644年)」に「淫者割其勢」との記述がある。
さらに「全国マン・チン分布考(インターナショナル新書、2018年、集英社)」によれば、江戸時代に「まら」に「勢」の字を当てている事例が見られるとのこと。一例として、平賀源内の「痿陰隠逸傳(1768年)」で使われている「白勢(しろまら)」を示している。
ここからは仮説。
となると、「金勢」を訓読みにすると「かなまら」ということになる。江戸時代の随筆「耳袋」にも津軽方面の「かなまら」についての記述がある。歴史は古くはないが、川崎の「かなまら祭」をはじめ、男根のご神体を「かなまら様」という例は、現在も残っている。
そもそも、「かなまら様」という神様があって、「金勢」の字が当てられたのではないだろうか。それが「こんせい」と読まれるようになり、様々な字を当てられていく。つまり、「コンセイ」の起源は「かなまら」であると考えられるのである。