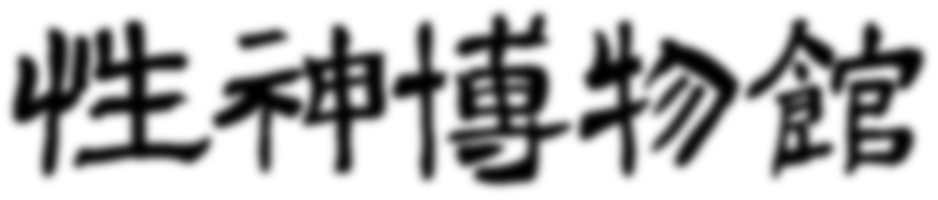男根形石棒と盆踊りの関係
形態 :縄文期の石棒
住所 :長野県佐久穂町
問合せ :0267-86-2041(佐久穂町公民館)
諏訪神社の御柱というのは、どうやら長春の「空の柱」あたりにその源流がありそうだというところまで行きつきました。そして、イザナギとイザナミの2神が子づくりのためにグルリまわった「天の御柱」も、やはり同じ流れのなかにあるんでしょう。
もっとも、「天の御柱」のほうは縄文時代中期から盛んに信仰された男根形石棒に影響されているという見方もできます。
「日本一大きい」とされる『北沢の石棒』を長野県の佐久穂町にでかけて拝見してきました。
高さ1.8m(実際の長さは2.23㍍あります)の男根形石棒が、青々とした田んぼの中におっ立っています。
この男根形石棒は1982(昭和57)年、それまで地面に転がっていたものを、「縄文時代はカクあったのではなかろうか」と、今のようなカタチにしたそうです。
勝手な想像ですが、この男根形石棒は、集落の広場の中央に立っていたのではないでしょうか。そして、年に何度かの祭りの日に、イザナギとイザナミが、「天の御柱」を回ったように、男女が輪になって踊り、気があった者たちが、近くの林の中へと消えて子づくりに励んだ。こんなふうにも考えられます。
やがて、この風習は歌垣や歌がいとなり(大きな樹木の下で行われた)、さらには盆踊りとなっていくんですね。男根形石棒は、太鼓を打ち鳴らす櫓ってわけです。