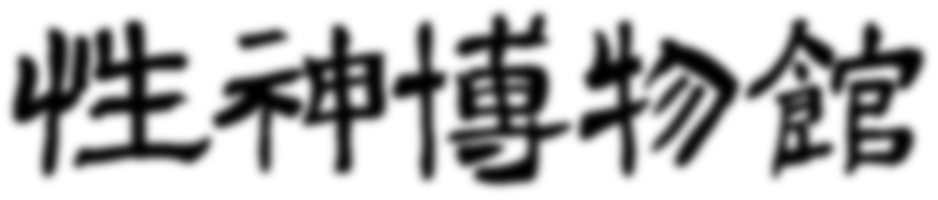西武新宿線・花小金井駅北口から北へ徒歩5分ほど。青梅街道の手前にある東京・小平市は円成院(黄檗宗)の境内に、「根勢大権現」と彫られた自然石の男根石が祀られている。背面には「安政五午歳 吉澤氏」と記されており、西暦1858年ごろに建てられたことが分かる。残念ながら住職さんが不在で取材はできなかったため、もともとこの場所にあったかは今のところ不明だが、記された名前は地元の農家であろうか(小平市のHPによると、この辺りの江戸時代の百姓に吉澤姓が見られるとのこと)。
左曲がり気味に反り返った男根の力強いフォルムを再現する、見事な自然の造形美。土の中か、それとも川底からか。こんな石が見つかれば、確かに祀りたくなるのもうなずける。
このコンセイ様が特徴的なのは、向かって左側にある「コブ」だ。現代でいえば、さしずめパール入りのバブル期男根か。キレイな真ん丸のコブが、埋め込まれたようにこんもり浮き上がっているのだ。
江戸時代にパール入りは、さすがになかったであろう。思うに、子種を宿す男根に備わったこのコブは、「子宝の象徴」ではないだろうか。農家が祀ったのであれば、ご多分に漏れず「子孫繁栄」「五穀豊穣」の祈願を込めていたであろうことは、想像に難くない。当時名字を名乗ることを許されている家ならば、なおさらである。
安政五年といえば、かの井伊直弼が大老に就任し、安政の大獄が始まった年である。黒船来航から5年以上がたち、庶民の間にも夷狄への不安が浸透していたかもしれない。同じ武蔵野が輩出した新撰組の近藤勇らも、もともとは攘夷派である。私見ではあるが、「コンセイシン」には「子孫繁栄」「五穀豊穣」とは別の側面があると考えられる。つまり、男根の強さ、エネルギーを要素とした「力の象徴」としての男根崇拝のかたちである。もしかすると「外敵に対する守護神」という思いもあったかもしれないが、いかがであろうか。
ちなみに、小平市の東端から西端へ青梅街道をずっと下っていくと、東大和市駅の手前に小平神明宮がある。この神社の境内にも「根勢大権現」が鎮座している。円成院とはちがい、石製の男根像に「根勢大権現」と彫られている。実は、「根勢」と表記する「コンセイ」様は他にあまり例がない。距離は離れているが、同じ小平市内にあるというのは興味深い。かつては、他にもあったのかもしれない。